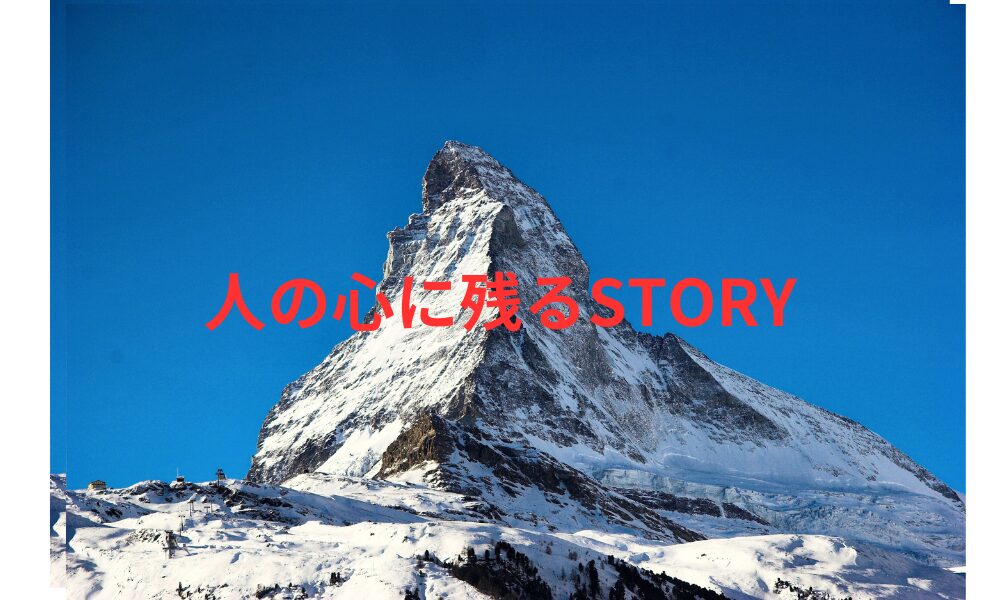1974年、フジテレビ系列のアニメドラマ『アルプスの少女ハイジ』が放送されました。
放送されて40年以上の時間を経ていますが、私たち視聴者が未だに視聴したくなるような万人の心を捉える作品とは、どのようなストーリーだったのでしょうか?
今回の記事では、『アルプスの少女ハイジ』の制作者の考えた作品を更に知ってもらい、ストーリーを楽しんでもらいたいと思っています。
高橋茂人:幼年期~青年期を過ごして
高橋茂人は、1924年生まれ。父親:茂雄は、栃木県の名士で、慶応大学では、ラグビー部で活躍して、将来的にはブラジルを開拓して、一旗上げようと志を立てていたが、断念し、映画の道に進んだ人です。
高橋にとって「ハイジ」に出てくるチーズ、ソーセージ、フランスパンなどの食物は、父親:茂雄が、中国の映画会社:華北電影に就業して、北京に呼び寄せられて以来、貴重な経験となっている。

この経験は、内地(日本国内)で暮らしていたら、経験できないことだった。
北京での生活スタイルは、たかが友達の家を訪ねるのに片道30分歩かねばならず、不便なので、一人息子の高橋にとって、自宅で読書のすることが多くなった。
ある時、父親:茂雄から「日本は、戦争に負けるから、お母さんと茂人は早く、内地(日本国内)へ帰れ!」とメッセージがあった。
高橋が帰国して、宇都宮の上野中学で学生生活を送っていた。その学校は、バンカラな校風でケンカが強い評判だった。
高橋は、担任の栗国先生から、慶応大学進学のため、3,4時間/1日で1年間の進学指導を受けた。
高橋は、1972年沖縄がアメリカ合衆国から日本に返還される前に、恩師:栗国先生の生まれ故郷を訪ねたが、中心地が、復興されず荒廃されたままだった。
高橋は、何の罪もない人々が死んで行くことが悲しくて、やりきれなかった。
高橋は、ケンカが強かったが、ヒロイズムに馴染めなかった。高橋の好む作品『ムーミン』、『ハイジ』などのヒューマン・ドラマを選ぶ理由になった。
高橋は、慶応大学に入学して、アイスホッケー部に入部して合宿によく持参していた岩波文庫の本がありました。当時、学生生活では、岩波文庫の本を愛読することが流行していた。
高橋は、大学のアイスホッケー部の活動の無い時期に、山岳部の友人と北アルプスや南アルプスの山々に登山に行っていた。
高橋自身が、よく愛読していた「アルプスの山の娘」=「ハイジ」だった。
「ハイジ」の原作の小説は、スイスの児童文学の作家:ヨハンナ・シュピーリの「ハイジの修業時代と遍歴時代」となる。
ヨハンナは、シュピーリ青年と結ばれて結婚するが、チューリッヒという都会の生活に馴染めなくて、心を病んでいた。
彼女は、病弱な一人息子と共にスイス東部の保養地:ラガーツ温泉に逗留していた。その逗留していた時に、ラガーツの自然や街並みor地元の人々の文化や暮らしぶりを丹念にメモして、後年小説を書く材料としていた。
また、この話題について、後に高橋たちが、「ハイジ」をアニメドラマのあらすじの一部としていました。ハイジの友人クララがこの保養地で自身の体調を回復させる場面がそうでした。
「ハイジ」をアニメドラマが日本人に広く知られるようになった理由

(1)ハイジ=純真無垢なイメージの女の子の人柄
(2)登山というスポーツが一般の人々に参加されるようになった
(3)スイス:永世中立国 戦争で心が傷ついた人々に癒しをもたらした
高橋茂人:社会人としてアニメーションの仕事に取り組んで
日本のテレビ文化の始まり
高橋は、1955年頃から就職活動を始めた。当時は、外国車の販売が流行していた。特に梁瀬自動車(現 ヤナセ)が、盛んに販売していた。
また、梁瀬自動車の子会社「日本テレビジョン株式会社」:テレビのコマーシャルを製作する会社。
梁瀬自動車の社長:梁瀬次郎は、アメリカの西海岸の街に軒並み立っているテレビ・アンテナを見つけて、『将来的には、日本国内でもテレビ放送が開始され、テレビ本体の需要が増える。』と、予想していた。
高橋は、1950年に日本テレビジョンに入社しました。
テレビ放送のスタート
1953年2月、日本で初めてのテレビ放送がNHKから始まった。放送がスタートした頃の一般家庭の収入では、テレビ本体を購入できないくらい高かった。
当時のテレビ放送を視聴するスタイルとしては、街頭テレビだった。駅前広場、盛り場、公園などでプロレスや相撲などのスポーツの試合の中継を視聴することが多かった。
テレビCMとアニメーション
アニメーションとは、元々止まっている絵や物を少しずつ動かして撮影し、繋いで、動いているようにみせる技法である。
具体例として、テレビアニメ、ジブリ映画、orデイズニー映画。
テレビCMの第1号は、時計メーカー:精工舎(現 セイコーホールディングス)の時報を知らせる働き。
アニメ画像のニワトリが時計のネジを巻いた後、実写の時計の映像が映し出され、時刻を知らせるシーンだった。
販売会社が、おススメの商品をアピールするのに、アニメーションを使うことは、私たち視聴者には、分かりやすく思われた。
高橋は、この会社に入社後、コマーシャルの制作現場で、絵を描いたり、フィルムを切り張りを覚えたりして得た経験、知識or人脈が、後年ハイジの制作に役に立った。
アニメーション技術の特徴
1)文字数の多い文章で説明するよりも、絵や漫画などの映像を利用する方が視聴者に分かりやすい。
2)文章にイラスト、チャート、グラフor地図などを加えて説明した方が分かりやすい。
3)キャラクターを使った説明。視聴者に印象付くけられやすい。

4)3Dアニメーション。視聴者に見せる画像に立体感を示して、より一層実写映像に近づけて、イメージしてもらえる。
高橋茂人:児童文学ムーミンがテーマの仕事をして
児童文学:ムーミンとは
ムーミンとは、フィンランドの作家:トーベ・ヤンソンによって創作されたキャラクターです。
「ムーミン・シリーズ」に出てくる登場人物は、小説、絵本、及び漫画などの作品に登場します。
1)ムーミン(ムーミントロール):好奇心旺盛で、率先して行動する人柄であり、ムーミン一家の中心人物です。
2)ムーミン・パパ:ムーミンの父親として、小説家であり、仕事以外では、ムーミン谷の探検をする冒険家であり、仕事と趣味のライフワークを愛しています。
3)ムーミン・ママ:愛する夫(ムーミン・パパ)、と我が息子(ムーミン)を愛して、一家の主婦兼母親であることを嬉しく、楽しく思っています。
ムーミンの世界は、登場人物が自然と共存して、様々な冒険を繰り広げる物語であり、読者にも学べることが魅力です。読者の皆様、どうか楽しみましょう!
トーヤ・ベンソンの世界観とヒッピー文化
トーベ・ヤンソンは、フィンランドの作家で、ムーミン・シリーズの作者として知られています。
彼女の作品は、自然、冒険、友情そして人間の心の成長をテーマにしています。
ムーミンの登場人物たちは、愛と平和を大切にし、自由な精神で世界を探究しています。
また、ヒッピー文化とは、1960年後半にアメリカ合衆国で登場した文化を担った若者を指します。
その若者たちは、アメリカ合衆国・サンフランシスコ、ヘイトアシュベリー地区に住んでいた。
彼らは、戦争や徴兵制に反対し、音楽、麻薬や非暴力運動を通じて対抗しようとしていました。
東洋思想にも興味を持ち、自然、愛、平和、セックス、自由を追求していました。
ムーミン:原作とアニメ作品の違い
1)絵のタッチが違う
原作の絵は、悲壮感を強く感じさせる一方、アニメ作品は、可愛らしい映像に映し出されている。これは、イギリスの新聞社が原作を依頼した時、大人向けに条件を付けた為である。
2)ミイとスナフキンの関係
原作では、ミイとスナフキンは、種違いの姉弟関係という設定です。母親が同じで父親が違う複雑な親子関係です。
アニメ作品では、ミイは、ムーミンと一緒に暮らしていたが、スナフキンは、友人として始まっています。
3)スナフキンの名前
日本のアニメでは、「スナフキン」の名前は、人気のある登場人物です。原作では、「スヌスムムリク」が、本当の名前です。
スェーデン語から英訳すると「スナフキン」となり、日本語は、英訳と同じ呼び方で有名になった。
また、原作では、スナフキンは、子供であり、喫煙しながら釣りを楽しむシーンが描かれていますが、アニメでは、スナフキンは大人という設定になっています。
4)人間関係の複雑さ
原作では、主人公のムーミン以外の登場人物が全て「移民=他の土地から引っ越してきた住民」です。そのため元々居た住民から「よそよそしい」雰囲気が感じられます。
アニメでは、このような複雑な人間関係が省かれています。
その他後続アニメ作品の特徴
児童文学を原作としたアニメは、絵本や児童小説などの文学作品を元に制作されたアニメ作品です。
世界名作劇場:児童文学をアニメ化したシリーズで、様々な作品が放送されました。これらの作品は、子供たちが、楽しみながら学びや感動を提供しています。
1)アンデルセン物語 アンデルセンが書いた童話をアニメ放送では、妖精のキャンティとズッコが紹介する。
2)ペリーヌ物語 フランスの作家:エルトール・アンリ・アルリーマロの原作『アル・ファミーユ(家族と共に)』。
3)小さなバイキング ドイツの作家:ルーネル・ヨンソン原作の児童文学のアニメ作品。主人公のビッケは、自分が小さくて弱くても、知恵と工夫で強敵に立ち向かう姿勢が素晴らしい。
4)山ねずみロッキーチャック アメリカの作家:ソーントン・バージェスの『バージェス・アニマル・ブックス』原作。森の動物たちが主人公の物語。主人公のロッキーと恋人ポリーの普段の生活を描いたり物語です。
ハイジを制作していた人たち
海外ロケーション・ハンティングの狙い
1)リアルな風景の描写
ハイジの舞台となるアルプスの山々の風景や村々を忠実に描くために、制作スタッフは、スイス・ドイツを訪問しました。視聴者により一層身近な描写に受けっとてもらうためです。

2)物語ロケ地を再現
ハイジの暮らしていた山小屋や村など実在する場所を忠実に描いています。特にマイエンフェルトの街並みや特徴をロケハンを行うことで再現することができました。
3)制作スタッフの体験
現地の取材をすること自体、制作スタッフにとっては貴重な体験となりました。現地の取材で多くの情報を取り入れ作品で表現することは、日本以外の視聴者にも興味を持ってもらうことになった。
4)視聴者に興味を持ってもらう
ハイジの制作以前の作品は、ロケ地での取材などを行った事例を聞いたことがないので、当時として前例がなかったと思われます。前例がない作品には、視聴者にとっては、より一層の素晴らしい作品を視聴することを期待するものです。
なお、スイスのマイエンフェルトは、今でも観光地として多くの人が訪れています。
ハイジの主題歌を作詞作曲した人たち
ハイジの主題歌「おしえて」。歌手は、伊集加代子(現、伊集加代)で、作詞家が、岸田衿子です。
主 題 歌 の 特 徴
番組の始まりで、視聴者の心を物語の舞台となるスイスへ誘うのに、大した効果があったのは、この曲の前奏、間奏及び後奏で流れるヨーデルである。
ヨーデルとは、スイスの東アルプス地方に昔から伝わる裏声を使った独特の歌い方である。
ヨ ーデ ル 歌 手 を 探 す
ハイジの番組の企画制作を始めたプロジューサーの高橋茂人は、大学に在学中に登山部に所属し、ヨーデルの歌声に馴染みがあったので、主題歌にはヨーデル歌手の参加もしてもらいたかった。
日本国内ではヨーデル歌手が探しても、いなかったので、スイス現地で見つけて、録音することになった。
録音場所は、スイス最大の都市:チューリッヒ。この街で出会った歌手が、シュワルツ親子で、母親:フレネリ、娘:ネリーであった。
このヨーデル歌手の親子は、エンディング曲「おしえて」には娘のネリー、終わり曲「待っててごらん」には親子の歌声が入っているそうです。
ハイジのアニメ・デザインを考案した人の仕事
アニメ作品の登場人物(キャラクター)は、どの様にして、出来上がるのか調べてました。
小田部羊一さんがハイジのデザイナーとして、取り組んでおられた事をインタビューした記事がswissinfo.chで掲載されていたので、引用させて頂きます。
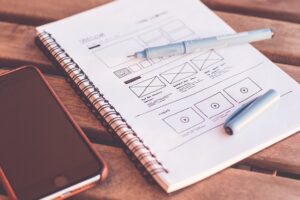
小田部さんご自身がされるお仕事で、登場人物の元となる人物or物は、現地のお土産品の人形、身近な人の人柄、映画出演者の特徴などを参考にして、作っておられると聞きます。
また、別の記事では、ハイジの作品に出てくる登場人物の特徴が掲載されているので、参考にさせていただいて、まとめてみました。
まとめ:様々な情報からわかってきたこと
『アルプスの少女ハイジ』のアニメ作品について
1)高橋茂人のプロフィール
2)日本のテレビ文化の変革
3)ハイジの作品が出来上がるまで過程
以上3点を中心に説明してゆきましたが、読者の方にはこの作品の素晴らしさが、わかりましたでしょうか?参考になれば、幸いでございます。